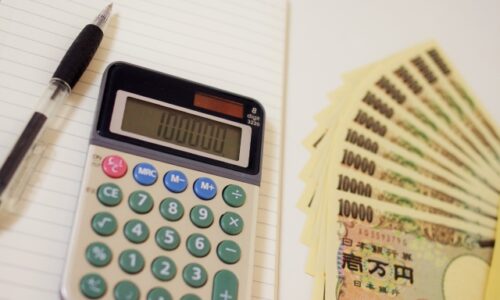「ひきこもり白書」の監修を務めた、
流通科学大学専任講師の新雅史さんの話をまとめてみました。
ひきこもりの実態については国が2015年と18年に5000世帯を対象に調査を行い、
ひきこもりの人や過去にひきこもっていた人の割合を推定していますが
クローズアップされるのは、その数だけです。
しかし、ひきこもりの数に目を向けるだけではなく、
ひきこもりの中の多様性に目を向け、
その実態を把握することが必要であると問題提起した。
ひきこもりUX会議では、
17年に女性のひきこもり当事者を対象にした実態調査を実施しましたが
回答者の中には主婦だったり、家事手伝いといった、見過ごされてきた人が
多く存在することが分かった。
白書のもとになった19年の調査では、
ひきこもり経験やそのきっかけ・要因に加えて、
家族構成や学歴・職歴などについて尋ねることで、
ひきこもりの多様性を明らかにしようと試みました。
調査では
「ひきこもり」
であるか否かを本人の自認にゆだねています。
それは厚生労働省が定義する
「仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、
6カ月以上続けて自宅にひきこもっている状態」
が、いかに本人の自認と関係しているのかを知りたかったからです。
また、現在ひきこもっていなくても、
過去にひきこもりをけいけんした方も多くおられます。
こうした方々が、ひきこもりの経験を今どう捉えているのか、
それも分析したいと考えました。
当事者の問題関心
1686人の回答者からのは、各設問に対する回答と併せ、
自由記述欄に46万字にも上る意見をいただきました。
UX会議のスタッフ全員がそのすべてに目を通し、分析を試みました。
様々な実態が明らかになるなか、印象的だったのは、
ひきこもりの原因やきっかけの回答の中に、
ひきこもりに至る経過やひきこもりの長期化の要因が見えてきたことです。
ひきこもりの原因やきっかけは複数回答としたのですが、
多くの方が二つ以上の回答を選んでいました。
また、ひきこもり期間が長いほど、回答数が多くなるという結果になりました。
選択肢の中で
「心の不調・病気・障害」
を多くの方が選んでいますが、それを単一回答した人はわずか3.5%であり、
ほとんどの方が別の要因・きっかけも選んでいることが分かりました。
また、「いじめ」「不登校」を選択した人は、
ひきこもり期間が長くなる傾向がありました。
こうした実態は個々のインタビューから明らかにされてきましたが、
これだけの規模の調査から明らかになったのは初めてです。
UX会議の皆さんには当事者ならではの問題関心で
データに向き合ってほしいと伝えました。
こうした私の思いに応えてくれたUX会議のスタッフの努力があって、
多くの意義ある知見が導き出せたと思います。
実践を通し地域をつなぐ
白書の刊行にたどり着いて感じていることは、ひきこもりとは「状態」です。
より踏み込めば、社会や他社との関係性が途切れている状態といえます。
従って、なぜ関係性を遮断せざるを得なくなったのか、
そこに目を向ける必要があるように思います。
今回の調査では、回答者の99%が生きづらさを感じていると答え、
その生きづらさの理由に75%の人が
「自己肯定感」を挙げています。この「自己肯定感」の強さは、
それまでの人生で「欠けている部分」や「できないところ」に
焦点を当てられ続けてきたことを意味します。
「欠けている部分」を指摘するのではなく、今ある可能性に注目して、
関係性を築くこととそれが彼ら、彼女らと向き合うための最初の一歩でしょう。
UX会議の皆さんが、女子会などの居場所の活動を行っているのは、
そうした考えからだと思います。
「白書」は、ひきこもりをネガティブではない形で
社会の問題として据えなおすためのスタートになったと思います。
また、ひきこもりと向き合うための方向性も少なからず示すことができたはずです。
白書の知見をもとに、新しい実践が各地で生まれ、
その実践を通し地域がつなっていく、
それがUX会議の新たな目標となるでしょう。
とともに大切なことは家族の問題です。
これまでひきこもりは家庭内の問題として放置され、
十分な支援、情報を得られないケースもありました。
誤った情報によって状況が悪化することがあってはならないと思います。
一方、悩みながらも問題に向き合ってきた家族もいます。
そうした体験を共有する場をつくりつつ、その経験を社会に発信したい。
私も人間関係に苦しみ、ひきこもりを経験したことがあります。
心の声が誰にも届かず、悩み続けておりました。
しかし、同じ悩みに苦しんでいる人と出会い解決に至りました。
共有できる場が増え、すこしでも羽ばたける人が増えていってほしいものですね。